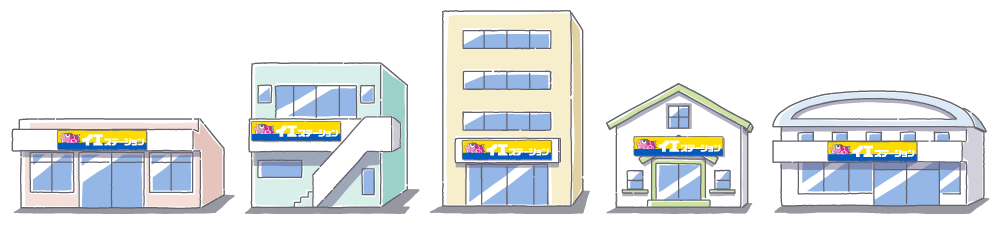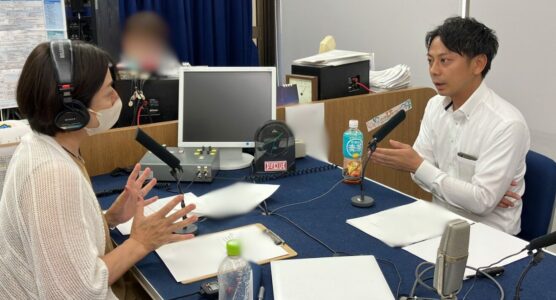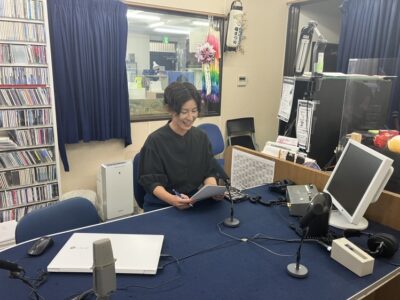「面倒くさい」は損のもと!
相続登記、放置するとどうなる?
昨年4月1日に施行された相続登記の義務化から、早くも一年が経過します。 「まだ大丈夫だろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、猶予期間は刻一刻と減っています!
相続登記は、亡くなった方から不動産を受け継いだ方に名義を変更する手続きのこと。 この手続きを怠ってしまうと、将来的に不動産を売却したくてもできなくなってしまう可能性があります。
なぜ相続登記が必要なの?
不動産は、誰のものなのかを法的に示す「登記」によって管理されています。 相続登記をしないままだと、不動産の名義は亡くなった方のまま。 これでは、新しい所有者として不動産を自由に活用することができません。
特に、不動産売却を検討されている方は要注意です! 相続登記が完了していなければ、買主との売買契約を締結することができないため、売却自体がストップしてしまいます。
「やり方がわからない」「面倒くさい」… そんなあなたへ!
相続登記の重要性は理解できても、「手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください!相続登記の流れは、決して複雑ではありません。 今回は、基本的な流れをわかりやすくご紹介します。
相続登記の流れ
- 相続人の確定: 誰が不動産を相続するのかを戸籍謄本などで確認します。
- 相続財産の調査: 相続する不動産の情報を確認します(登記簿謄本など)。
- 遺産分割協議(または遺言書の確認): 相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合います。遺言書がある場合は、その内容に従います。
- 必要書類の収集: 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、亡くなった方の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など、法務局で指定された書類を準備します。
- 申請書の作成: 法務局のホームページや窓口で申請書を入手し、必要事項を記入します。
- 法務局へ申請: 作成した申請書と必要書類を管轄の法務局へ提出します。
- 登記完了: 補正などがなければ、通常1~2週間程度で登記が完了します。
困ったら専門家にご相談を!
上記はあくまで基本的な流れであり、個々の状況によって必要な手続きや書類は異なります。 「自分でやるのは不安…」という方は、迷わず専門家にご相談ください。
司法書士は、相続登記の専門家です。書類作成から法務局への申請まで、全てを代行してくれます。 私たち不動産会社も、相続に関するご相談を承っております。不動産売却と合わせて相続登記についてもお気軽にご相談ください。
猶予期間が迫っています!
相続登記の義務化では、令和6年3月31日までに相続した不動産について、令和9年3月31日までの登記が義務付けられています。 また、令和6年4月1日以降に相続した不動産については、相続の開始を知った日から3年以内に登記する必要があります。
猶予期間があるとはいえ、手続きには時間と手間がかかります。 特に、相続人が多かったり、遠方に住んでいる方がいたりする場合は、手続きに時間がかかる傾向があります。
「まだ時間がある」と思わずに、早めの行動をおすすめします!
最後に
相続登記は、皆様の大切な財産を守るために必要な手続きです。 放置してしまうと、将来的に後悔する可能性もあります。
イエステーションでは、相続登記に関するご相談はもちろん、不動産売却に関するご相談を承っております。 「うちの場合はどうすればいいの?」 「何から始めたらいいかわからない」など、些細なことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。 皆様の不安を解消し、スムーズな不動産売却の手続きをサポートさせていただきます。
ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください
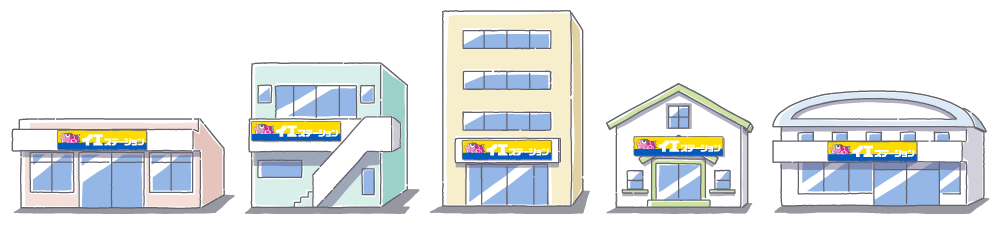
宮城県
福島県
茨城県
店舗一覧
当社でDXを推進するにあたり利用しているサイボウズ社のkintoneにて利用している株式会社ソニックガーデン様のツールを用いた改善事例について取り上げていただきました。
▶記事はこちらからご覧ください
▶他の取組みについてはこちらをご覧ください
不動産購入の流れを徹底解説!
物件探し~引き渡しまで
「いつかはマイホームを…」そう考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、不動産購入は人生の中でも特に大きな買い物であり、何から始めたら良いか分からず不安に感じる方もいるかもしれません。
この記事では、不動産購入の流れをステップごとに分かりやすく解説します。物件探しから契約、引き渡しまで、各ステップで注意すべきポイントや、知っておくと役立つ情報も満載です。この記事を読めば、不動産購入の全体像を把握し、安心してマイホーム購入に向けて準備を進められるでしょう。
ステップ1:購入計画を立てる
まずは、無理のない資金計画を立て、希望条件を整理することから始めましょう。
資金計画を立てる
・自己資金、住宅ローンの借入可能額、諸費用などを考慮して、購入予算を決めましょう。
・住宅ローンは、金融機関によって金利や審査基準が異なります。複数の金融機関を比較検討することが大切です。
・諸費用は、物件価格の3~7%程度が目安です。内訳は、仲介手数料、登記費用、印紙税、住宅ローン手数料、火災保険料などです。
希望条件を整理する
・エリア、広さ、間取り、築年数、駅からの距離、周辺環境、学校区など、希望条件をリストアップしましょう。
・家族構成やライフスタイルに合わせて、優先順位をつけることが大切です。
・希望条件は、将来のライフプランも考慮して決めましょう。
情報収集をする
・インターネットや不動産情報誌などで、物件情報を収集しましょう。
・不動産会社のウェブサイトや、住宅展示場なども参考になります。
・不動産ポータルサイトでは、希望条件に合った物件を絞り込んで検索できます。
・気になる物件があれば、不動産会社に問い合わせて資料請求や内覧予約をしましょう。
ステップ2:物件を探す
希望条件に合う物件を探しましょう。
不動産会社に相談する
・希望条件を伝え、物件を紹介してもらいましょう。
・不動産会社の担当者と信頼関係を築くことが大切です。
・地域に密着した不動産会社は、インターネットに掲載されていない情報を持っていることがあります。
・複数の不動産会社に相談し、比較検討することをおすすめします。
物件を見学する
・気になる物件は、実際に足を運んで見学しましょう。
・日当たり、周辺環境、建物の状態、設備などを確認します。
・内覧時には、チェックリストを持参すると便利です。
・周辺環境は、昼と夜で雰囲気が異なることがあります。時間帯を変えて見学することをおすすめします。
物件を比較検討する
・複数の物件を見学し、比較検討しましょう。
・希望条件に優先順位をつけ、最適な物件を選びます。
・物件の価格だけでなく、維持費や修繕費も考慮しましょう。
ステップ3:購入申し込み・契約
購入したい物件が決まったら、購入申し込み、契約へと進みます。
購入申し込みをする
・購入したい物件が決まったら、購入申し込みを行います。
・購入申し込み書に、購入希望価格や契約条件などを記入します。
・購入申し込みは、売買契約の締結を約束するものではありません。
重要事項説明を受ける
・不動産会社から、物件に関する重要な事項の説明を受けます。
・契約内容をしっかりと確認し、疑問点は質問しましょう。
・重要事項説明書は、契約前に必ず交付されます。重要事項説明の内容は、契約の判断材料となる重要な情報です。
不動産売買契約を締結する
・重要事項説明に納得したら、売買契約を締結します。
・契約書の内容をよく確認し、署名・捺印します。
・契約締結後、買主は売主に手付金を支払います。
・契約書には、売買代金、支払い方法、引き渡し時期、契約解除に関する事項などが記載されています。
ステップ4:住宅ローン契約
住宅ローンを利用する場合は、契約手続きが必要です。
住宅ローン審査を受ける
・金融機関の審査を受けます。
・必要書類を準備し、審査に臨みましょう。
・住宅ローン審査に必要な書類は、源泉徴収票、住民税決定通知書、本人確認書類などです。
・審査期間は、金融機関によって異なります。
住宅ローン契約を締結する
・住宅ローン審査に通ったら、金融機関と住宅ローン契約を締結します。
・金利タイプや返済方法などを確認し、契約内容を理解しましょう。
・住宅ローン契約には、金利、返済期間、返済方法、保証料、団体信用生命保険などが記載されています。
ステップ5:残金決済・引き渡し
残金決済が完了したら、物件の引き渡しを受けます。
残金決済をする
・売買契約で定められた期日までに、残金を支払います。
・金融機関からの融資実行と同時に行うことが一般的です。
・残金決済時には、司法書士が立ち会い、登記申請に必要な書類を確認します。
物件の引き渡しを受ける
・物件の状態を確認し、問題がなければ引き渡し完了です。
・引き渡し時には、物件の鍵、付帯設備の取扱説明書、建築確認済証などが渡されます。
登記申請をする
・所有権移転登記などの登記申請を行います。
・司法書士に依頼することが一般的です。
・登記申請には、登録免許税、司法書士報酬などがかかります。
ステップ6:引越し・入居
引越し準備をし、新居での生活をスタートさせましょう。
引越し準備をする
・引越し業者を選定し、引越し準備を進めます。
入居する
・新居での生活をスタートさせます。
確定申告をする
・住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告を行います。
不動産購入の注意点
・不動産購入は、時間と労力がかかるものです。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
・不動産会社や金融機関など、専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。
・契約内容をしっかりと確認し、不明な点は必ず質問しましょう。
・購入後も、固定資産税や修繕費などの費用がかかります。
まとめ
不動産購入は、人生における一大イベントです。この記事の各ステップを理解し、事前に準備をすることで、安心して理想のマイホームを手に入れることができるでしょう。
しかし、不動産購入は多くの時間と労力を要するプロセスでもあります。時には、予期せぬ問題に直面することもあるかもしれません。
イエステーションでは、各金融機関や税理士などの信頼できる専門家を紹介することが可能ですので、ご自身での手配が不要となり、購入までの流れがスムーズに進みます。イエステーションで、あなたにとって最高の住まいを見つけましょう。
ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください
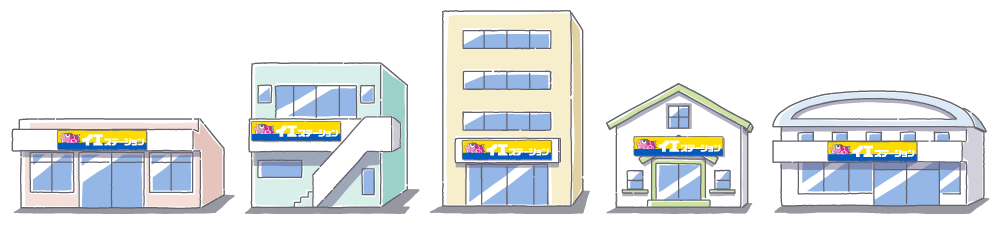
宮城県
福島県
茨城県
店舗一覧
お客様の背景
売主様
氏名:S.Y様
ご職業:会社員
お住いの地域:愛知県
ご相談地域:会津若松市
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:K.M様
ご職業:無職
お住いの地域:郡山市
ご相談地域:会津若松市
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
「相続したのですが県外に住んでいて、そのままの状態で。誰も住んでいなくて今後も利用する予定はありません。インターネットを見て、イエステーションさんがこのエリアに精通していると出てきたので問い合わせしました。」とご相談をいただきました。
買主様
希望エリアは会津若松市。自己資金で購入できるお家を探されておりました。父と一緒に同居の為に探しているので部屋数は多くなく利便性の良い立地がご希望でした。
ご提案した解決策
売主様
まずは、会津若松市の相場・売却にかかる諸費用をお伝えさせていただきました。また今後の固定資産税などの維持管理費用の負担が、売却をすればなくなります。それらの経費は、今後弊社が担うことをお伝えすると「会社としてこのリスクを負ってくれるんだね。理解しました。肩の荷がおりました。ありがとう。」と感謝の言葉をいただきました。
買主様
自己資金で購入できる物件をご提案いたしました。また、リフォームも弊社で担うことができますので、修繕希望はすぐに」見積を提示。引っ越し希望時期まで2カ月くらいの期間でしたが、リフォームの日程も後手後手にならず、希望日時までにお引き渡しができました。
担当営業より

イエステーション 白石店
吉井 裕昭
不動産は日数が経つにつれて価値が下がってしまいます。一人で悩まずにご相談だけでも結構です。一緒に解決策を考えましょう!
この担当者がいる店舗情報
お客様の背景
売主様
氏名:S.Y様
ご職業:会社員
お住いの地域:愛知県
ご相談地域:会津若松市
問い合わせ方法:インターネット
買主様
氏名:K.M様
ご職業:無職
お住いの地域:郡山市
ご相談地域:会津若松市
問い合わせ方法:インターネット
ご相談内容
売主様
「相続したのですが県外に住んでいて、そのままの状態で。誰も住んでいなくて今後も利用する予定はありません。インターネットを見て、イエステーションさんがこのエリアに精通していると出てきたので問い合わせしました。」とご相談をいただきました。
買主様
希望エリアは会津若松市。自己資金で購入できるお家を探されておりました。父と一緒に同居の為に探しているので部屋数は多くなく利便性の良い立地がご希望でした。
ご提案した解決策
売主様
まずは、会津若松市の相場・売却にかかる諸費用をお伝えさせていただきました。また今後の固定資産税などの維持管理費用の負担が、売却をすればなくなります。それらの経費は、今後弊社が担うことをお伝えすると「会社としてこのリスクを負ってくれるんだね。理解しました。肩の荷がおりました。ありがとう。」と感謝の言葉をいただきました。
買主様
自己資金で購入できる物件をご提案いたしました。また、リフォームも弊社で担うことができますので、修繕希望はすぐに」見積を提示。引っ越し希望時期まで2カ月くらいの期間でしたが、リフォームの日程も後手後手にならず、希望日時までにお引き渡しができました。
担当営業より

イエステーション 白石店
吉井 裕昭
不動産は日数が経つにつれて価値が下がってしまいます。一人で悩まずにご相談だけでも結構です。一緒に解決策を考えましょう!
この担当者がいる店舗情報
新生活に向けた住まい選び!
中古住宅・中古マンション
・新築を徹底比較!
3月は新しい生活が始まる季節。進学や就職、転勤などで環境が変わる方も多いのではないでしょうか。そんなタイミングだからこそ、住まいについて改めて考えてみるのも良い機会です。
「今の家賃は適正なのか?」「もっと快適な住まいに引っ越したい」「資産として持ち家を検討したい」
――そんなお悩みをお持ちの方へ、今回は 新築物件・中古住宅・中古マンションの特徴を比較し、それぞれのメリット・デメリットを詳しくご紹介します。あなたにとってベストな住まい選びのヒントになれば幸いです。
1. 中古住宅:個性と費用対効果を重視する方向け
中古住宅とは、過去に人が住んでいた、もしくは建築後に入居者が一度も入居していない住宅のことです。一般的には、新築住宅に比べて価格が安く、物件数も豊富です。
【メリット】
1.魅力的な価格帯
新築と比較すると大幅に費用を抑えられるのが最大の強みです。余った予算をリフォームや家具の購入に回すことができます。住宅ローンの負担も軽減できるため、家計の余裕が生まれやすいでしょう。
2.豊富な選択肢
築年数や間取り、立地など、さまざまなタイプの物件から選べます。市場に出回っている物件数も多いため、じっくり探せば希望に合う物件に出会える可能性が高まります。
3.実際の住み心地の確認
内覧時に日当たりや風通し、周辺環境などを事前に確かめられるため、入居後のギャップを減らせます。季節や時間帯によって変わる住環境も把握しやすいでしょう。
4.広い物件の可能性
築年数によっては、同じ予算でも新築より広い物件が見つかることがあります。特に都心部では土地の広さや建物の規模に大きな差が出ることも少なくありません。
【デメリット】
1.物件ごとに異なる建物状態
築年数に応じて、修繕費用がかかる場合があります。購入前にホームインスペクション(建物診断)を実施して、隠れた問題がないか調べておくことをおすすめします。
2.耐震性・断熱性の課題
1981年以前の旧耐震基準で建てられた物件は、耐震性に不安が残ることがあります。断熱性能が低い住宅では、光熱費が高くなる可能性も考慮すべきです。これらの改修には追加費用がかかります。
3.住宅ローン控除の制限
新築と比較して、住宅ローン控除の条件が厳しくなる場合があります。築年数や耐震基準によって適用される条件が変わるため、事前に確認が必要です。
2. 中古マンション:利便性とコミュニティを重視する方向け
中古マンションとは、過去に人が住んでいた、もしくは建築後に入居者が一度も入居していないマンションのことです。一般的には、新築マンションに比べて価格が安く、駅近などの利便性の高い物件が多い傾向があります。
【メリット】
1.優れた立地環境
駅から近い場所や商業施設が充実したエリアなど、利便性の高い立地に物件が多く存在するのが中古マンションの大きな魅力です。通勤や買いものに便利な環境を手に入れやすいでしょう。
2.安心の管理体制
管理会社が共用部分の清掃や修繕を担当するため、戸建てと比べて維持管理の手間がかかりません。管理の質は物件によって異なるため、管理組合の運営状況も確認しておくとよいでしょう。
3.素晴らしい眺望
高層階の物件では、開放的な眺めを楽しめる場合があります。景観の良さは住み心地に大きく影響するため、重要なポイントになります。
【デメリット】
1.管理費・修繕積立金の負担
毎月の費用負担が発生します。将来的な値上げも考慮する必要があります。修繕計画や積立金の状況を確認し、長期的な費用計画を立てておきましょう。
2.駐車場の問題
駐車場がない、または空きがない場合があります。車を所有している方は、駐車場の確保や月額料金も考慮に入れる必要があるでしょう。
3.限られた専有面積
戸建てと比較すると、専有面積が狭くなる傾向があります。家族構成や将来的なライフスタイルの変化も考慮して検討しましょう。
3. 新築:最新設備と快適性を求める方向け
新築とは、建築後1年未満で、まだ誰も入居していない住宅のことです。最新の設備やデザインが魅力で、住宅ローン控除などの税制優遇も充実しています。
【メリット】
1.最新の設備とデザイン
快適な住環境で、現代的な設備やデザインを取り入れた暮らしができます。省エネ家電や最新の住宅設備が標準装備されていることが多く、生活の質が向上します。
2.高水準の耐震性・断熱性
最新の建築基準で建てられているため、安心して長く住めます。省エネ性能も高く、光熱費の節約にもつながるでしょう。
3.充実した税制優遇
住宅ローン控除や贈与税の非課税措置など、税制優遇が手厚いです。長期優良住宅の認定を受けた物件ではさらに優遇される場合もあります。
4.注文住宅という選択肢
希望の間取りや内装にできる注文住宅という選択肢もあります。完全にオーダーメイドの住まいを実現できるのは新築ならではの魅力です。
【デメリット】
1.高い購入費用
中古と比較して、購入費用が高くなります。土地代や建築費の上昇により、近年はさらに価格が上昇傾向にあります。
2.少ない選択肢
人気のエリアでは、希望する物件が見つからない場合があります。立地条件と予算のバランスを取るのが難しいケースも多いでしょう。
3.入居までの待ち時間
完成まで時間がかかるため、すぐに入居できない場合があります。建築中の物件を購入する場合は、仮住まいの費用も考慮する必要があります。
4.現物確認の難しさ
購入前に実物を見られない場合があります。モデルルームや図面、VRなどで確認することになりますが、実際の住み心地は入居後に分かる部分もあります。
まとめ
- 中古住宅: 費用対効果を重視し、自分らしさを反映するリノベーションを楽しみたい方におすすめです。
- 中古マンション: 利便性を重視し、駅近などの便利な暮らしを求める方におすすめです。
- 新築: 最新の設備や快適性を重視し、長期間安心して住みたい方におすすめです。
最後に
不動産購入は、人生における大きな決断です。それぞれの良い点と気をつけるべき点を比較検討し、あなたの生活スタイルや将来計画に合った最適な住まいを見つけてください。購入前には必ず複数の物件を見学し、専門家のアドバイスも参考にすることをおすすめします。
初めて確定申告する方へ
今年は3月17日(月)まで‼
「確定申告」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどのような手続きをすればいいのか分からない方も多いでしょう。本記事では、初めての方に向けて、確定申告の準備から申告方法までを詳しく解説します。
1. 確定申告とは?
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得にかかる税金を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
確定申告が必要な方:
●個人事業主・フリーランス
●不動産所得や株の売買による所得がある方
●給与所得が2,000万円を超える方
●医療費控除や住宅ローン控除を受けたい方
●副業での所得が20万円を超える方
通常、会社員は会社が年末調整を行うため、確定申告は不要です。
2. 確定申告の準備
2024年度分の確定申告期間は、2025年2月17日から3月17日までです。
①必要書類の準備
確定申告に必要な書類は、所得の種類や控除の内容によって異なります:
●確定申告書
●源泉徴収票
●各種控除の証明書(医療費・生命保険料控除など)
●本人確認書類(マイナンバーカードなど)
●収入証明書類(売上・報酬の証明)
●経費証明書類(領収書・レシート)
②申告方法の選択
確定申告の主な申告方法:
- 税務署に直接申告
- 郵送による申告
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)による申告
e-Taxのメリット: 自宅からインターネットで申告可能
③会計ソフトの活用
個人事業主やフリーランスは、会計ソフトの活用をおすすめします。日々の帳簿付けから確定申告書作成まで効率的に行えます。
3. 確定申告の流れ
STEP1:必要書類の準備
●源泉徴収票、控除証明書を集める
●医療費控除の領収書をまとめる
●個人事業主は帳簿付けと決算書作成
STEP2:確定申告書の作成
作成方法:
●国税庁ウェブサイトの確定申告書作成コーナー
●確定申告ソフト
●e-Taxでのオンライン作成
e-Tax利用に必要なもの:マイナンバーカード、ICカードリーダー(スマホからカードリーダーなしで申請することも可能)
STEP3:税務署への提出
提出方法:
●税務署に持参
●郵送
●e-Tax
ポイント: 確定申告期間中は窓口が混雑するため、e-Taxがおすすめ
STEP4:納税または還付
●税金の納付(金融機関、コンビニ、クレジットカード、e-Tax)
●還付金は指定口座に振込
STEP5:書類保管
●確定申告書と関連書類は5年間保管
●税務署からの問い合わせに備える
4. 不動産を売却した方の確定申告
土地や建物を売却した場合、譲渡所得金額(利益)が発生すると確定申告が必要となります。譲渡所得金額は以下の計算式で求めます。
【譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額(利益)】
?譲渡価額
譲渡価額とは、土地や建物を売却して得た金額のことです。不動産の売買契約書に記載されている金額が基本となります。
?取得費
取得費は、売った土地や建物を購入したときにかかった費用の合計額です。建物については、減価償却費相当額を控除する必要があります。
取得費として認められる主な項目:
●不動産の購入代金
●購入時の仲介手数料
●購入に関わる登記費用
●不動産取得税
●購入後に行った改良費用
?譲渡費用
譲渡費用は、不動産を売却する際に直接かかった費用です。
譲渡費用として認められる主な項目:
●売却時の仲介手数料
●測量費用
●売却に関わる登記費用
●売却のための広告費
●建物の取壊し費用
※特例制度について
マイホーム売却時の特例:
●一定の要件を満たす場合、3,000万円の特別控除などの特例が適用できます
●マイホーム売却で損失が出た場合、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算できる特例があります
一般の不動産売却における注意点:
●通常の不動産売却で損失(譲渡所得金額がマイナス)が生じても、他の所得との損益通算はできません
●長期所有(5年超)と短期所有で税率が異なります
確定申告の際は、不動産の売買契約書や領収書など、取引を証明する書類を準備しておくことが重要です。特例の適用を検討している方は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
5.まとめ
確定申告は、事前準備と正確な情報があれば、決して難しい手続きではありません。個人事業主やフリーランス、副業所得者、不動産売却者など、様々な立場の方に関わります。申告準備では必要書類の収集と申告方法の選択が重要で、e-Taxなどオンライン申告が便利です。特に不動産売却時は譲渡所得の計算と特例制度の理解が必須となります。申告書類は5年間保管し、期限内に適切に手続きを行うことで、余計な負担や追徴課税のリスクを避けられます。専門家のサポートも積極的に活用しましょう。