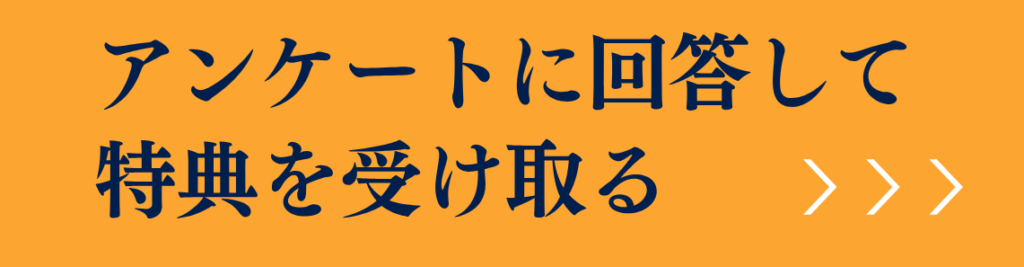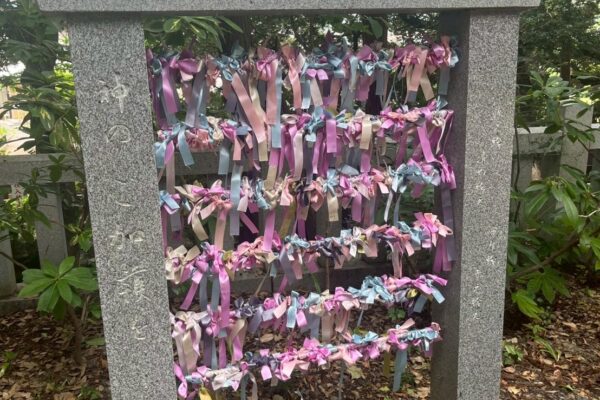投稿トップ


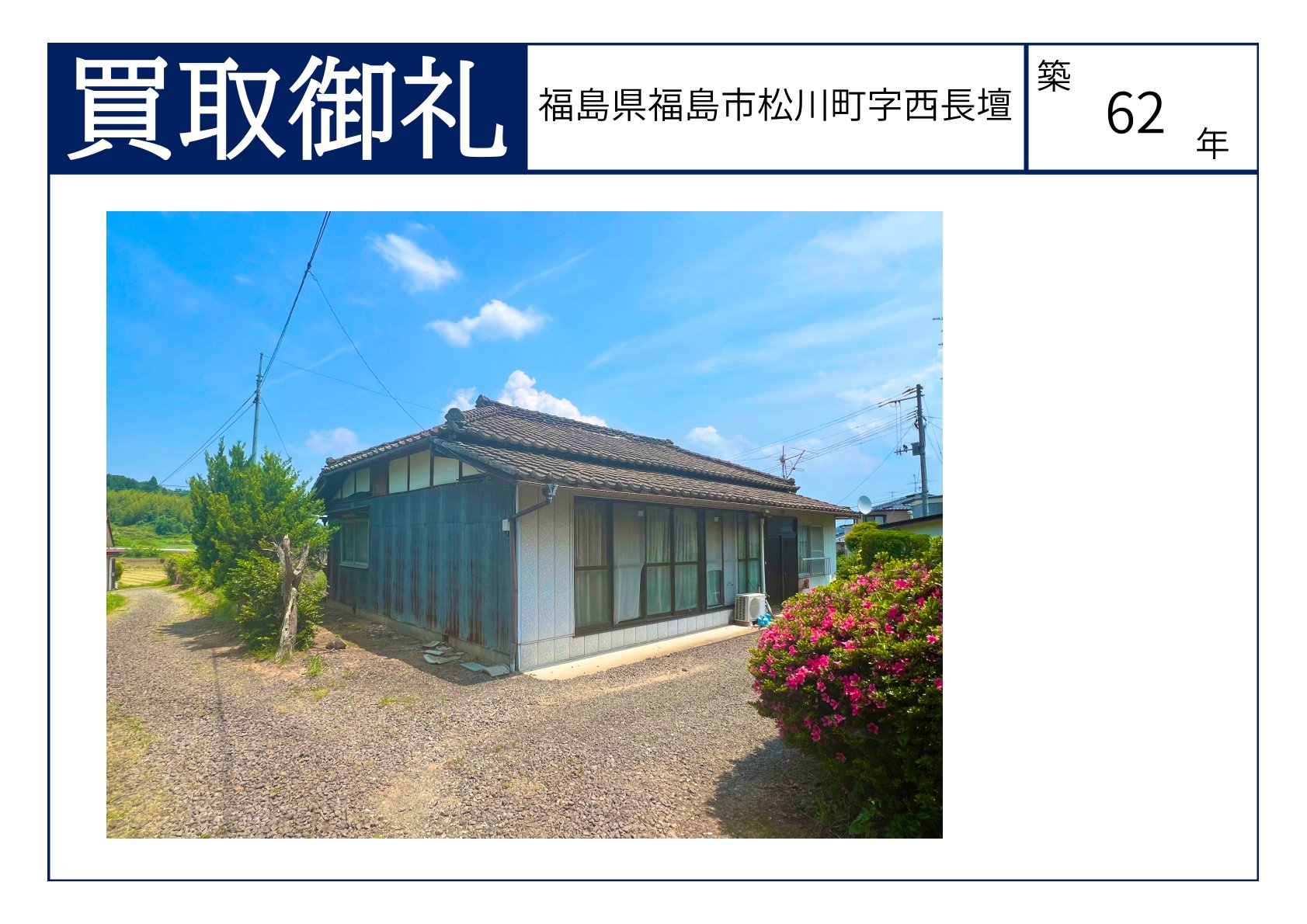


最近、日本各地で地震が頻発しています。2025年6月には、鹿児島県で最大震度5弱を観測する地震が発生し、その後の余震活動など、わたしたちの住む日本が地震大国であることを改めて痛感させられる出来事が続いています。いつ、どこで大きな地震が起きてもおかしくない状況の中で、「もしも」の時にあなたの命と財産を守るための備えはできていますでしょうか?
地震発生時、まずわたしたちの身に危険が及ぶのは、室内に設置された家具や家電の転倒、落下、移動によるものです。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、家具の転倒による死傷者が多数報告されており、室内の安全対策は防災の第一歩と言えます。
今回は、地震発生時に慌てないための具体的な家具の転倒防止対策に焦点を当て、さまざまなアイデアをご紹介します。ご家族やご自身の状況に合わせて、ぜひ今一度、室内の安全対策を見直してみてください。
1. 家具の固定:揺れに強い部屋を作る基本
地震の揺れで家具が倒れるのを防ぐためには、壁や天井にしっかりと固定することが最も重要です。市販の防災グッズを上手に活用しましょう。
ポール式器具やL字金具でしっかり固定
背の高いタンス、食器棚、本棚などは、地震の際に転倒しやすい家具の代表です。これらには以下の方法で対策しましょう。
・ポール式器具(突っ張り棒タイプ):家具と天井の間に突っ張って固定するタイプです。設置は比較的簡単ですが、天井の強度や家具の高さに合わせて適切な長さのものを選びましょう。家具と天井の間に隙間ができないよう、しっかりと突っ張ることが重要です。
・L字金具(アングルタイプ):家具の天板や側面を壁に直接ねじ止めするタイプです。最も強力な固定方法とされています。取り付ける際は、壁の裏にある柱や間柱にねじ止めすることが必須です。石膏ボードの壁に直接ねじ止めすると効果が薄いため、専用のアンカー(壁の中に挿入してねじを固定する部材)を使用するか、専門業者に相談しましょう。
連結金具で一体感を出す
複数の家具を横に並べている場合、地震の揺れでそれぞれがバラバラに動いて倒れる可能性があります。
・連結金具:隣り合う家具同士を連結金具でつなぎ、一体化させることで、転倒のリスクを減らすことができます。これにより、個々の家具が独立して揺れるのを防ぎ、全体としての安定性を高めます。
開き戸には耐震ラッチを
食器棚や吊り戸棚の開き戸は、地震の揺れで勝手に開き、中の食器や物が飛び出してくる危険があります。
・耐震ラッチ:地震の揺れを感知すると自動でロックがかかり、扉が開くのを防ぐ金具です。後付けできるタイプも多く、ホームセンターなどで手軽に入手できます。中の物が飛び散るのを防ぐだけでなく、避難経路を塞ぐ事態も防げます。


2. 家具の配置の見直し:安全な空間を確保する
家具を固定するだけでなく、配置を工夫することも地震時の安全性を高める上で非常に重要です。
避難経路の確保
・玄関や窓の周り:地震発生後、速やかに避難できるように、玄関や窓への経路には家具を置かないようにしましょう。また、家具が倒れて扉の開閉を妨げない配置になっているか確認してください。
・通路の確保:室内の主要な通路には、倒れやすい家具や背の高い家具を置かないようにし、広めのスペースを確保しましょう。
寝室・子供部屋の安全確保
就寝中に地震が起きた場合、倒れてきた家具で負傷する危険性が高まります。
・背の高い家具の配置:寝室や子供部屋には、できるだけ背の高い家具を置かないのが理想です。もし置く場合は、ベッドや布団から離れた場所に配置するか、頭上に落ちてこないような工夫(たとえば、ベッドの足元側に配置するなど)を凝らしましょう。
・重いものの収納:引き出しがある家具の場合、重いものは下段に収納し、重心を低くすることで転倒しにくくなります。
ガラス製品の飛散防止
窓ガラスや食器棚のガラス扉は、地震の揺れで割れて破片が飛び散り、深刻な怪我の原因となります。
・飛散防止フィルム:ガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで、万が一割れても破片が飛び散るのを防ぎ、負傷のリスクを低減できます。DIYで貼れるタイプも多く販売されています。
・厚手のカーテン:窓には厚手のカーテンを閉めておくことで、ガラスが割れた際の衝撃を和らげ、破片の飛散をさらに防ぐ効果が期待できます。
3. 家電製品の転倒・移動防止:見落としがちな対策
大型のテレビや冷蔵庫などの家電製品も、地震の揺れで転倒したり移動したりする危険があります。
滑り止めや粘着マットでピタッと固定
・耐震ジェルマット(粘着マット):テレビ、電子レンジ、小型の棚などの下に敷くことで、揺れによる滑りや転倒を防ぎます。さまざまなサイズや形状があり、目立たない透明なタイプもあります。設置面に粘着するため、定期的にホコリを取り除き、粘着力を維持しましょう。
・滑り止めシート:洗濯機の下や食器棚の中の食器類の下に敷くことで、滑りや散乱を防ぎます。
固定ベルトやワイヤーでしっかり固定
・テレビ用固定ベルト:特に大型の薄型テレビは重心が高く、転倒しやすい傾向があります。専用の固定ベルトで壁やテレビ台に固定することをおすすめします。多くの場合、テレビ背面のネジ穴を利用して取り付けられます。
・冷蔵庫用固定ベルト:冷蔵庫も大型で重いため、地震の揺れで大きく動き、転倒する可能性があります。壁に固定するベルトやワイヤーで対策しましょう。
4. その他の安全対策アイデア:普段から意識したいこと
家具や家電の直接的な固定以外にも、日頃から意識しておきたい安全対策があります。
寝室にはスリッパを常備
・枕元にスリッパや靴:地震の揺れでガラスや食器が割れ、床に散乱する可能性があります。夜中に地震が起きた際に素足で歩いて怪我をしないよう、寝室の枕元やベッドの下に、すぐに履ける丈夫なスリッパや靴を置いておきましょう。
火災防止対策も忘れずに
家具の転倒とは直接関係ありませんが、地震による二次災害で最も恐ろしいのが火災です。
・感震ブレーカーの設置:大きな揺れを感知すると自動的に電気を遮断する感震ブレーカーを設置することで、停電からの復旧時に発生する通電火災を防ぐことができます。これは、阪神・淡路大震災でも多くの火災の原因となった現象であり、非常に有効な対策です。
・消火器の設置と点検:各家庭に消火器を設置し、家族全員がその場所と使い方を把握しておきましょう。定期的に点検し、使用期限が切れていないかを確認することが重要です。
家族で定期的に話し合いを
・防災会議の開催:家具の配置や固定状況は、家族構成の変化や模様替えなどで変わることがあります。年に一度は家族全員で「防災会議」を開き、室内の安全対策を点検し、改善点がないか話し合う機会を設けましょう。
・危険箇所の共有:小さな子どもがいる家庭では、どの家具が危険か、どこに近づいてはいけないかなどを具体的に教え、家族全員で危険箇所を共有しておくことも大切です。

最後に
地震はいつ起こるかわかりませんが、日頃からの備えをしっかり行うことで、被害を最小限に抑え、大切な命を守ることができます。ご紹介した「家具の転倒防止!安全対策アイデア集」を参考に、今日からできる対策を始めてみませんか?
防災対策は一度行ったら終わりではありません。常に最新の情報を入手し、ご自身の環境に合わせて対策を更新していくことが重要です。あなたとあなたの大切な人の命を守るために、今すぐ室内の安全対策を見直しましょう。
ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください
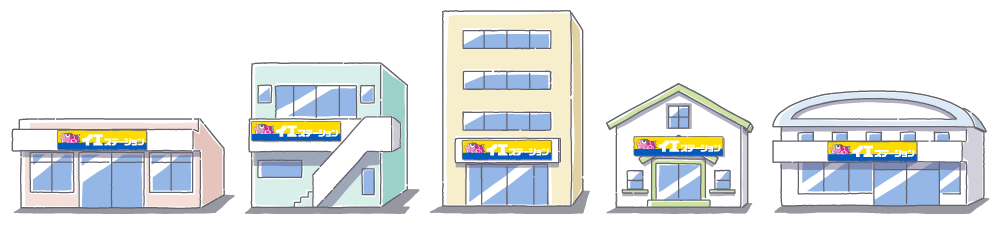
宮城県
福島県
茨城県
※お盆前必見※
実家の未来はこれで決まる!
家族会議の秘訣
ご実家の未来を考える家族会議。前記事のチェックリストで現状を把握し、課題が見えてきたと思います。次は具体的な行動に移る番です。各項目で「はい」と「いいえ」、どちらにチェックが付いたかによって、次のステップは大きく変わります。
今回は、前記事のチェックリストの答えから、それぞれの状況に応じた具体的な行動を見ていきましょう。
STEP1:話し合いの前に!「実家の今」を知ることから始めましょう
☐ 「今の実家、ズバリいくらで売れるの?」
【はい】(すでに査定を受けている場合)
査定結果を家族会議で共有し、その価格について全員で話し合いましょう。複数の査定を受けている場合は、それぞれの価格や担当者の説明を比較検討し、なぜその価格なのかを深く理解することが重要です。この価格を基準に、売却の是非や、売却後の資金計画を具体的に検討できます。
【いいえ】(まだ査定を受けていない場合)
まずは複数の不動産会社に無料査定を依頼しましょう。これは、売却の意思がなくても、実家の客観的な価値を知るための第一歩です。インターネットの一括査定サイトなどを活用すると、効率的に複数の査定を受けられます。
☐ 「今、不動産市場って高いの?安いの?」
【はい】(市場状況を把握している場合)
把握している市場状況(例:現在は売り手市場で高値で売却できる可能性がある、など)を家族会議で共有しましょう。その情報が、実家を売却するか、賃貸に出すか、維持するかといった意思決定にどう影響するかを議論する材料となります。
【いいえ】(市場状況を把握していない場合)
不動産会社に査定を依頼する際に、合わせて現在の不動産市場の状況(売り手が多いか、買い手が多いか、価格のトレンドなど)を詳しく質問しましょう。また、不動産関連のニュースや専門サイトなどで情報収集することも有効です。
STEP2:いざ、家族会議!「このお家、これからどうする?」
❶実家の「今」を整理しよう!
☐ 「家の中はどんな状態?」
【はい】(状態を把握している場合)
把握している家の状態(例:水回りの劣化、壁のシミなど)を家族会議で具体的に共有し、修繕が必要な箇所と、その修繕費用の概算について話し合いましょう。特に、売却や賃貸を検討する場合、どの程度の修繕が必要か、費用対効果はどうかを議論する材料になります。
【いいえ】(状態を把握していない場合)
家族で実際に家の中をくまなく見て回り、客観的な視点で「手入れが必要な場所」を具体的にリストアップしましょう。写真に撮っておくと、離れて暮らす家族とも共有しやすくなります。
☐ 「維持費ってどれくらいかかってる?」
【はい】(維持費を把握している場合)
把握している維持費(固定資産税、光熱費、保険料など)を家族会議で共有し、「今後、誰が、どのように負担していくか」について具体的に話し合いましょう。 特に、実家を維持する選択をする場合、この負担は長期にわたるため、公平な分担が重要です。
【いいえ】(維持費を把握していない場合)
過去1年分の固定資産税の納税通知書、電気・ガス・水道の検針票、火災保険料の書類などを集め、年間の維持費を正確に算出しましょう。必要であれば、自治会費やケーブルテレビ料金なども含めて確認します。
☐ 「今、誰が住んでる?将来も住み続ける予定?」
【はい】(居住者の意向を把握している場合)
居住者の「住み続けたい」「引っ越したい」といった意向を家族会議で共有し、その意向を最大限尊重した上で、実家の未来の選択肢(売却、賃貸、維持など)を検討しましょう。特に「住み続けたい」という意向が強い場合は、どうすればそれが可能かを具体的に議論します。
【いいえ】(居住者の意向を把握していない場合)
まずは居住者本人(親など)と一対一で、本人の気持ちを最優先にじっくりと話し合いましょう。 家族会議の前に、本人の正直な気持ちや希望を聞き出すことが非常に重要です。プレッシャーを与えず、傾聴の姿勢で臨みましょう。
☐ 「家の中の荷物はどれくらい?」
【はい】(荷物の量を把握している場合)
把握している荷物の量(特に不要なものや、残しておきたい思い出の品など)を家族会議で共有し、具体的な片付けのスケジュールや、不用品の処分方法、思い出の品の分配について話し合いましょう。 遺品整理や生前整理を視野に入れる場合、業者への依頼も検討できます。
【いいえ】(荷物の量を把握していない場合)
家族で実際に家の中(特に物置、押し入れ、屋根裏、納戸など)を確認し、大まかな荷物の量を把握し、リストアップしてみましょう。この際、ゴミの量、残しておきたい物の量などを分類すると、より具体的な話し合いにつながります。
☐ 「この家、誰のもの?」
【はい】(名義人を把握している場合)
把握している登記名義人を家族会議で共有し、その名義人が話し合いに参加しているかを確認しましょう。複数名義人がいる場合は、全員の同意が必要であることを再確認し、意見を調整する場を設けます。
【いいえ】(名義人を把握していない場合)
市区町村の法務局で「登記事項証明書」を取得し、正確な名義人を確認しましょう。これは誰でも取得可能です。
☐ 「あの親戚が口出ししてくるかも…?」
【はい】(口出しする可能性のある親戚がいる場合)
家族会議の前に、「親戚への対応方針」を具体的に決めましょう。 例:「家族会議で決まったことを後日報告する」「意見は聞くが、最終決定は私たち家族が行う」など。感情的にならず、一貫した態度で接することが重要です。
【いいえ】(口出しする可能性のある親戚がいない場合、または対応不要と判断した場合)
特に次の行動は不要ですが、万が一の事態に備え、家族間で情報共有の体制を整えておくと安心です。
❷家族みんなの「これから」を話し合おう!
☐ 「今後、実家をどうしたい?全員の希望は?」
【はい】(全員の希望を把握している場合)
各々の希望(売却、賃貸、維持、空き家など)を比較検討し、それぞれのメリット・デメリットや、実現可能性について具体的に議論しましょう。意見が分かれる場合は、妥協点や代替案を探ります。
【いいえ】(全員の希望を把握していない場合)
家族会議の場で、時間をかけて全員が自由に「実家をどうしたいか」という正直な気持ちを語り合う機会を設けましょう。各々の思いや価値観を共有することが第一歩です。
☐ 「もし実家を維持するなら、誰が中心になって管理や費用を負担する?」
【はい】(管理・費用負担を明確にしている場合)
決定した役割分担と費用負担について、書面(家族間での合意書など)に残し、定期的に見直す機会を設定しましょう。家族の状況や家の状態は変化するため、柔軟に対応できる仕組みづくりが大切です。
【いいえ】(管理・費用負担を明確にしていない場合)
実家を維持する場合の具体的な役割分担(例:庭の手入れ、光熱費の支払い、郵便物の確認など)と、費用負担の割合を明確に話し合い、決めましょう。
☐ 「将来的に、この家でどんなことをしたい?」
【はい】(将来のビジョンを共有している場合)
共有しているビジョン(例:リフォームして住む、子孫に残す、地域に貢献する)を実現するための具体的なステップと、それに必要な費用、労力、時間などを検討しましょう。必要であれば、リフォーム業者や建築士に相談することも視野に入れます。
【いいえ】(将来のビジョンを共有していない場合)
家族会議で、「この家が将来どうなっていたら嬉しいか」という長期的な視点で、それぞれの夢や希望を自由に話し合いましょう。 写真や雑誌などを使ってイメージを共有するのも良いでしょう。
☐ 「もし空き家になったら、どうやって管理する?」
【はい】(空き家管理方法を検討している場合)
決定した管理方法(自主管理、業者委託など)について、具体的な実行計画を立てましょう。 自主管理であれば、巡回頻度や担当者、業者委託であれば、契約内容や費用などを確認します。
【いいえ】(空き家管理方法を検討していない場合)
空き家になった場合のリスク(劣化、防犯、近隣トラブルなど)を共有し、自主管理が可能か、または空き家管理サービスなどの専門業者に依頼すべきかを検討しましょう。各方法のメリット・デメリット、費用などを情報収集します。
☐ 「もし相続が発生する場合、話はどこまで進んでる?」
【はい】(相続について話し合っている場合)
現在の相続の進捗状況(遺言書の有無、遺産分割協議の状況など)を家族会議で共有し、不明な点や課題があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談する準備を進めましょう。
【いいえ】(相続について話し合っていない場合)
まずは「親が元気なうちに」相続に関する基礎知識(法定相続人、遺留分など)を家族全員で共有し、遺言書の有無などを確認しましょう。そして、税理士や弁護士といった専門家への相談を強く検討しましょう。生前対策(生前贈与、家族信託など)についても情報収集を始めます。
❸具体的な一歩を踏み出そう!
☐ 「リフォームは必要?どこを修繕する?」
【はい】(リフォーム箇所と費用を検討している場合)
具体的なリフォーム業者を絞り込み、見積もりを取り、契約内容や工期、費用、保証などを細かく確認しましょう。家族間で最終的な合意形成を行い、実行に移します。
【いいえ】(リフォームが必要か検討していない場合)
まずは専門家(リフォーム業者や建築士)に相談し、現状診断と修繕箇所の提案、概算費用を出してもらいましょう。 「売却」「賃貸」「居住」といった目的を伝えれば、それに合った提案をしてくれます。
☐ 「空き家になったら、管理はどうする?」
【はい】(管理方法を決めている場合)
決定した管理方法(自主管理なら具体的なスケジュールと担当者、業者委託なら契約手続き)を実行に移しましょう。必要であれば、近隣住民への挨拶や緊急連絡先の共有も行います。
【いいえ】(管理方法を決めていない場合)
上記の「もし空き家になったら、どうやって管理する?」の【いいえ】の行動に移り、早急に管理方法を検討・決定しましょう。
☐ 「相続のこと、税金のこと、誰に相談する?」
【はい】(相談先を検討している、または相談している場合)
検討している専門家(税理士、弁護士、司法書士など)に具体的に連絡を取り、相談のアポイントメントを取りましょう。 家族会議で共有した情報(登記事項証明書、資産状況など)を持参するとスムーズです。
【いいえ】(相談先を検討していない場合)
売却や相続、贈与には様々な税金や法的手続きが伴います。まずは**「誰に相談すべきか」を明確にするために、それぞれの専門家の役割を理解し、適切な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)をリストアップ**しましょう。
☐ 「売るなら、ズバリいくらで売りたい?」
【はい】(売却希望価格を決めている場合)
決めた売却希望価格を不動産会社に伝え、売却活動を開始しましょう。 価格設定の根拠(査定額、市場動向、資金計画など)を明確にすることで、不動産会社も適切な戦略を立てやすくなります。
【いいえ】(売却希望価格を決めていない場合)
無料査定で提示された適正価格や市場動向を参考に、家族全員が納得できる売却希望価格を具体的に話し合いましょう。 感情論ではなく、客観的なデータに基づいて設定することが重要です。
☐ 「いつ頃、売りたい?」
【はい】(売却時期を決めている場合)
決定した売却時期(例:来年春までに、など)を不動産会社に伝え、具体的な売却スケジュール(内覧開始、契約、引き渡しなど)を立ててもらいましょう。 これに合わせて、片付けや引っ越しの準備を進めます。
【いいえ】(売却時期を決めていない場合)
引っ越し先との兼ね合い、家族の状況(親の体調、子どもの入学など)、市場動向などを考慮して、具体的な売却時期の目安を家族で話し合って決めましょう。
☐ 「引っ越し先はどうする?」
【はい】(引っ越し先を検討している場合)
検討している引っ越し先(賃貸、購入、施設など)について、具体的な情報収集を進め、内覧や見学、問い合わせなどを行いましょう。 売却と並行して進めることで、スムーズな住み替えが可能です。
【いいえ】(引っ越し先を検討していない場合)
まずは「どんな住まいに住みたいか」「どこに住みたいか」といった具体的な条件を家族で話し合い、リストアップしましょう。賃貸か購入か、地域、広さ、予算など、具体的な条件を明確にすることが第一歩です。
ご実家の未来に関する話し合いは、一朝一夕には終わらないことも多いでしょう。しかし、一つひとつの項目について「はい/いいえ」で次の行動を明確にすることで、着実に前進することができます。
イエステーションでは、ご家族の皆さんの気持ちに寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

限られた住空間を最大限に活用するために、収納ボックスは欠かせないアイテムです。ただ、やみくもに購入するだけでは、期待通りの効果は得られません。ここでは、収納ボックスの賢い選び方から実践的な活用術まで、整理収納のプロの視点も踏まえながら詳しくご紹介します。
収納ボックス選びの基本原則
まずは目的を明確にしましょう
収納ボックスを選ぶ上で最も大切なのは、**「何をどこに収納するのか」**をはっきりさせることです。見た目だけで選んでしまうと失敗につながりやすいため、収納したいモノと置く場所を具体的にイメージすることから始めましょう。
衣類、書類、子ども用品など、収納するモノによって最適なボックスの種類やサイズは異なります。また、クローゼットの中か、リビングの目に触れる場所かによって、デザインや色の選び方も変わってきます。
サイズ選びは慎重に
サイズ選びで後悔しないためには、設置場所の寸法を正確に測ることが不可欠です。高さ、横幅、奥行きを測り、引き出しやフタの開閉がスムーズにできるかも確認しましょう。
特に奥行きは重要です。押入れなら66~74cm、クローゼットなら55~60cmが一般的です。これらの基本サイズを押さえておくと、スペースを最大限に有効活用できます。
素材別の特徴とメリット・デメリット
プラスチック製収納ボックス
メリット:
・軽量で持ち運びが楽
・水に強く、汚れにくい
・手頃な価格で種類が豊富
・透明タイプは中身が見える
デメリット:
・通気性が悪く、湿気がこもりやすい
・静電気でホコリがつきやすい
・安価なものは強度が不足している場合がある
プラスチック製は最も普及しており、初心者でも扱いやすい素材です。子どものおもちゃや掃除用品など、湿気をあまり気にしないアイテムの収納に適しています。
布製・不織布製収納ボックス
メリット:
・軽量で折りたたんで収納できる
・通気性が良い
・柔らかな素材でインテリアになじみやすい
・クローゼットの上段などに最適
デメリット:
・水に弱い
・型崩れしやすい
・重いモノの収納には不向き
布製や不織布製は、オフシーズンの衣類や軽量なアイテムの収納に最適です。使わない時はコンパクトにたためるのも魅力です。
紙製収納ボックス
メリット:
・環境に優しい素材
・デザイン性の高い商品が多い
・不要になった際の処分が簡単
デメリット:
・湿気に弱い
・重いモノの収納には不向き
・長期的な使用にはあまり向かない
バンカーズボックスのような紙製収納ボックスは、書類整理や一時的な収納に向いています。



タイプ別収納ボックスの選び方
フタ付きタイプ
フタ付きタイプは、ホコリから守りたいモノや長期保管したいモノ、人に見せたくないモノの収納に最適です。クローゼットの上段や押入れの奥など、頻繁に出し入れしない場所での使用に向いています。
引き出しタイプ
引き出しタイプは、頻繁に出し入れするアイテムの収納に便利です。積み重ねて使えるため、縦の空間を有効活用できます。衣類収納で特に人気が高く、中身が見やすく取り出しやすいのが特徴です。
オープンタイプ
オープンタイプは、使用頻度の高いアイテムや見せる収納に適しています。モノの出し入れが簡単で、子どもでも使いやすいのがメリットです。
実践的な活用術とアイデア
収納ボックスを最大限に活用するには、ただモノを入れるだけでなく、それぞれの場所やモノの特性に合わせた工夫が重要です。
リビング収納の工夫
リビングは家族が集まる場所であり、来客の目にも触れるため、見た目の美しさと機能性の両立が特に重要です。
・統一感を出す: 同じシリーズの収納ボックスで揃えると、すっきりとした印象を与えられます。色も白、ベージュ、グレーなどのナチュラルカラーを選ぶと、どんなインテリアにもなじみやすく、圧迫感もありません。
・「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける: 雑誌やリモコンなど、頻繁に使うものはオープンタイプのボックスやデザイン性の高いバスケットに入れ、「見せる収納」として活用しましょう。一方、細々としたモノや生活感の出るコード類などは、フタ付きのボックスや引き出しタイプの収納に入れて「隠す収納」にすることで、リビング全体の清潔感を保てます。
・子どものおもちゃ収納: リビングに子どものおもちゃがある場合、大きめのオープンボックスをいくつか用意し、ざっくりと種類別に収納できるようにすると、子どもも自分で片付けやすくなります。キャスター付きのボックスなら、移動も簡単で掃除の際にも便利です。
キッチン収納の活用法
キッチンはモノが多くなりがちですが、収納ボックスを上手に使えば、効率的で使いやすい空間に変えられます。
・食品ストックの整理: 調味料や乾物、レトルト食品などのストックは、半透明や透明のプラスチックボックスに入れると、中身が一目瞭然で賞味期限の管理も楽になります。種類ごとにボックスを分けることで、必要なものをサッと取り出せるようになります。
・調理器具や消耗品の収納: 引き出しの中は仕切り付きのボックスやファイルボックスを活用し、菜箸、お玉、ピーラーなどの調理器具を立てて収納すると、取り出しやすくなります。また、ラップやアルミホイルなどの消耗品も、立てて収納できるボックスを使うとデッドスペースを減らせます。
・冷蔵庫内の整理: 冷蔵庫内も収納ボックスで仕切ると、食品が迷子にならず、整理整頓しやすくなります。野菜室には深めのボックスを使い、種類別に立てて収納すると鮮度を保ちやすくなります。
子ども部屋の整理術
子ども部屋の収納は、子どもが自分で片付けやすい仕組みを作ることが最も重要です。
・軽くて安全な素材を選ぶ: プラスチック製や布製のボックスは、軽くて持ち運びやすく、万が一ぶつかっても怪我の心配が少ないためおすすめです。
・ざっくり収納を意識する: 細かく分類しすぎると子どもにはハードルが高くなります。「ブロック用」「ぬいぐるみ用」など、大まかな分類でオープンタイプのボックスを用意すると、子どもが自分でポイポイと入れやすくなります。
・カラフルなボックスで楽しさを演出: 子どもが楽しみながらお片付けできるよう、カラフルな収納ボックスを選んだり、お気に入りのキャラクターのラベルを貼ったりするのも効果的です。
・成長に合わせて見直す: 子どもの成長とともに遊び方や持ち物も変わるため、定期的に収納を見直し、ボックスの用途や配置を調整しましょう。
クローゼット収納の最適化
クローゼット収納は、スペースを最大限に活かし、衣類や小物の出し入れをスムーズにすることがポイントです。
▼「上段」「中段」「下段」で使い分け:
・上段: 使用頻度の低いモノや軽いモノ(オフシーズンの衣類、来客用寝具、思い出の品など)は、ホコリよけのフタ付きで、軽量な不織布ボックスや布製ボックスに収納すると良いでしょう。
・中段: 頻繁に使う衣類や小物(日常着、バッグなど)は、取り出しやすい引き出しタイプの収納ケースや、オープンタイプのワイヤーバスケットなどを活用しましょう。衣類は立てて収納するとシワになりにくく、取り出しやすくなります。
・下段: 重いモノや、形状が変わりやすいモノ(ジーンズ、靴、掃除機など)は、丈夫なプラスチックケースやキャスター付きのボックスに収納すると便利です。
▼ハンガーパイプ下の活用: パイプ下に引き出しタイプの収納ケースを置くことで、ワンピースやロングコートなどの下にも無駄なく収納スペースを確保できます。
▼デッドスペースの活用: クローゼットの扉裏にフックを取り付けて、バッグやベルトなどを吊るす収納も有効です。また、吊り下げ式の収納ボックスを使えば、棚がない場所でも収納スペースを作れます。


収納ボックス活用の成功ポイント
ラベリングの重要性
収納ボックスには必ずラベルを貼りましょう。中身が不明なボックスは、結局使われなくなってしまうことが多いです。テプラやマスキングテープを使って、見やすくおしゃれにラベリングすることで、家族全員が使いやすい収納になります。
詰め込みすぎない
収納ボックスは、容量の8割程度で使用するのがベストです。満杯に詰め込んでしまうと、取り出しにくくなり、使い勝手が悪くなってしまいます。
定期的な見直し
3か月に一度は収納の見直しを行いましょう。使わなくなったアイテムは処分し、収納方法も生活スタイルの変化に合わせて調整することが大切です。
まとめ
収納ボックスは、選び方と使い方次第で住環境を劇的に改善できる優れたアイテムです。まずは目的と設置場所を明確にし、適切なサイズと素材を選びましょう。そして、ラベリングや適切な容量での使用を心がけることで、長く使える収納システムを構築できます。
完璧な収納を一度に作ろうとせず、少しずつ改善を重ねていくことが成功の秘訣です。今回ご紹介したポイントを参考に、あなたのライフスタイルに合った収納ボックス活用術を見つけてください。快適で整理された空間は、毎日の生活をより豊かにしてくれるはずです。
ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください
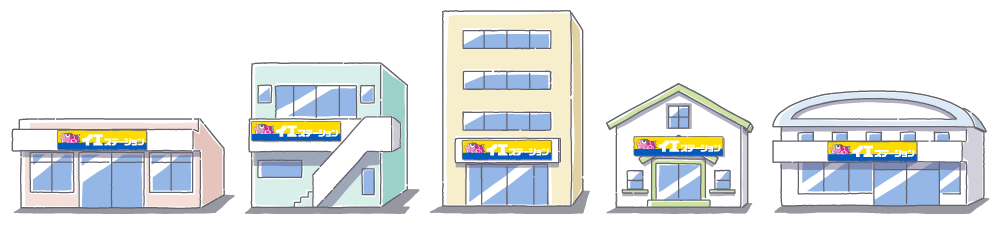
宮城県
福島県
茨城県

「そろそろ家を売却したいけれど、何から始めたら良いかわからない…」
「一体、自分の家はいくらで売れるのだろう?」
「高く売るにはどうしたら良いの?」
もしあなたが今、このようなお悩みをお持ちでしたら、朗報です。
この度、あなたの不動産売却の不安を解消し、「早く」「損なく」「後悔なく」不動産売却を成功させるための
【無料!7日間メール集中講座】を開催することになりました!
この講座では、プロの不動産エージェントが、これまで培ってきた知識とノウハウを惜しみなく公開します。毎日1通、あなたの不動産売却を成功に導くための実践的な情報をお届けします。
【こんな方におすすめです】
- 相続した空家を売りたいけど、何から手をつけていいか分からない方
- 自分の不動産の適正価格を知りたい方
- できるだけ早く・損なく・後悔なく土地やお家を売りたい方
- 売却に伴う税金や費用に不安がある方
- 信頼できる不動産会社を見つけたい方
【この講座で学べること(一部をご紹介)】
- 1日目: 知らないと損する?!不動産売却、まず「査定」から始める理由
- 2日目: 高く売るなら「今」を知れ!不動産市場のトレンドを徹底解説
- 3日目: あなたの不動産を早期売却・高値売却するための≪鍵≫
- 4日目: 知らないと損!不動産契約の「落とし穴」を徹底解説
- 5日目: 仲介手数料だけじゃない!売却にかかる全費用を徹底解説
- 6日目: あなたの売却を成功に導く!「良い不動産会社」の見つけ方
- 7日目: 一歩踏み出すあなたへ!無料売却相談のご案内
この講座は、 通常有料で提供している専門知識を今回特別に【無料】でご提供します。
それは、より多くの方に質の高い情報をお届けするため。そこで・・・
\\お願いがあります//
今後の講座内容をさらに充実させるために、簡単なアンケートにご協力いただけませんか?
たった1分のアンケートにお答えいただくだけで、この価値ある7日間無料メール集中講座をすぐに受講できます。
開催期間は【7月1日~7月7日】の7日間限定!
最終日の七夕の日には、それまでの学びを活かし、あなたの不動産売却に関する「願い」を叶えるサポートをさせていただきます。
締め切りが迫っています。この貴重な機会を、ぜひ、お見逃しなく!