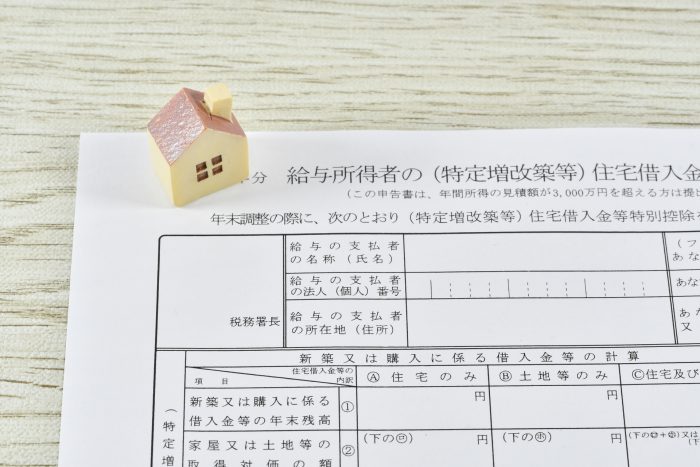
令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱に、住宅ローン減税延長(令和8年度から5年間)が盛り込まれました。
住宅ローン減税は住宅ローン返済の負担を軽減してくれる心強い制度ですので、マイホームの購入・住み替えなどを検討している場合には、詳しい内容を確認しておきたいですよね。
今回は宮城県・福島県・茨城県で年間900件以上の不動産取引をサポートしているイエステーションが、令和8年度からの住宅ローン減税をわかりやすく解説します。
住宅価格の上昇が続く中で、住居費用の負担感を抑えながら理想のマイホームを手に入れるために、ぜひ最後までごらんください。
※令和8年度の住宅ローン減税の詳細は、令和8年3月末までに決定されます。
当記事は現時点で公表されている情報をもとに作成しており、政府などからの情報発信を受けて内容を更新していきます。
宮城県・福島県・茨城県でスムーズなマイホーム購入・住み替えなどをご希望の方は、イエステーションへご相談ください。
目次
Toggle住宅ローン減税は令和8年度から5年間延長

令和8年度以降の住宅ローン減税が税制改正大綱に盛り込まれましたが、令和7年度までの住宅ローン減税とは内容が違うため、法律の改正が必要です。
〈参考〉国土交通省『住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~』
そのため令和8年1〜3月は、「住宅ローン減税に関する法律の改正案作成〜改正法案成立」を待つ状況となります。
令和8年度の住宅ローン減税の内容が決まるまでの流れは、以下のとおりです。
| 時期 | ステップ |
|---|---|
| 各省庁が「令和8年度税制改正要望」を提出 | |
| 各省庁・税制調査会が、税制改正に向けて要望を検討 | |
| 「令和8年度税制改正大綱」の決定・公表 | |
| 令和8年1月〜3月 | 税制改正大綱にもとづいて、財務省が「税制改正法案」を作成し、国会に提出 ↓ 衆議院・参議院が審議後に本会議へ進む ↓ 衆議院・参議院の本会議で可決 ↓ 「税制改正法案」が成立。このとき、令和8年度以降の住宅ローン減税施行日も決定 |
| 令和8年4月 | 令和8年度以降の住宅ローン減税を施行 |
〈参考〉財務省『税制改正のプロセスについて教えてください。』
令和8年度の住宅ローン減税に関する情報は国土交通省・財務省などから公表されるため、当記事では今後も動向を確認し、最新情報をお伝えしていきます。
宮城県・福島県・茨城県でマイホームの住み替えなどをご希望の方は、イエステーションへお問い合わせください。
地域最大級の不動産売買実績を活かし、不動産売買をサポートいたします。
住宅ローン減税適用の基本条件・令和8年度からの新しい条件|新築・中古購入・リフォームなど

住宅ローン減税を活用するためには、詳細な条件をクリアする必要があります。
令和8年度以降の住宅ローン減税は条件が緩和される見込みですが、令和7年度までの条件と変わらない基本条件もあるため、「基本条件」「令和8年度からの新しい条件」をそれぞれ確認しましょう。
※現時点で政府が公表している最新情報を紹介するため、今後変更される可能性があります。
令和8年度からの住宅ローン減税|基本条件
住宅ローン減税は所得税の減税制度で、住宅ローンを利用して新築・リフォームなどをした以下の条件を満たす方のみに適用されます。
| 住宅ローンの利用目的 | 適用条件 |
| 新築住宅の購入 | ①規定された省エネ住宅※1を購入 ②新築から6ヶ月以内に入居し、年末まで居住 ③所得2,000万円以下 ④住宅ローンの返済期間が10年以上 ⑤(2つ以上の住宅所有者)主に居住する住宅 ⑥過去3年間・以後3年間に譲渡所得の課税の特例※2を受けていない ⑦特別な関係(配偶者・直系血族など)の方以外から住宅を購入 |
| 買取再販住宅(宅建業者が規定の増改築をして再販した中古住宅)の購入 | ・上記①〜⑦に該当 ・築10年以上の住宅 ・リフォーム後2年以内にご自身が購入 ・リフォーム額が購入額の20%以上 ・大規模修繕など100万円以上or一定のバリアフリー改修など50万円以上の工事 ・新耐震基準の耐震性能を持つ住宅 ・建築後、使用されていた住宅 ・贈与された住宅ではない |
| 中古住宅(買取再販住宅以外)の購入 | ・上記③〜⑦に該当 ・購入から6ヶ月以内に入居し、年末まで居住 ・新耐震基準の耐震性能を持つ住宅 |
| ご自宅の増改築(大規模修繕など工事内容に規定があります) | ・上記③〜⑥に該当 ・増改築から6ヶ月以内に入居し、年末まで居住 ・ご自身が所有・居住する住宅の増改築 ・100万円以上の増改築 |
| 現行の耐震基準に該当しない中古住宅の耐震改修 | ・上記③〜⑦に該当 ・中古住宅購入から6ヶ月以内に入居し、年末まで居住 ・贈与された住宅ではない ・建築後、使用されていた住宅 ・中古住宅の購入日までに規定の申請をし、入居までに現行の耐震基準に該当する証明書を取得している |
※1 省エネ住宅の種類は、次の章「令和8年度からの住宅ローン減税|新しい条件」で詳しく紹介します。
※2 「譲渡所得の課税の特例」とは、不動産の売却時に一定条件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を控除できる等の減税制度のことです。
〈参考〉国税庁ホームページ『土地・建物(住宅ローン控除等)』
令和8年度からの住宅ローン減税|新しい条件

令和8年度からの住宅ローン減税は、以下のような条件変更・追加などがあります。
| 新しい条件 | 注意点など |
|---|---|
| 【床面積に関する条件】 床面積40㎡以上 (新築・中古購入・リフォーム) | ・所得1000万円超の方は床面積50㎡以上 ・子育て世帯・若年夫婦世帯※1は床面積50㎡以上となる場合がある |
| 【省エネ性能に関する条件】 すべての新築住宅が住宅ローン減税の対象となるのは令和9年末まで (登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までの新築住宅も含む) | ・令和9年末までに建築確認を受けるすべての新築住宅は住宅ローン減税の対象 ・令和10年以降に建築確認を受ける新築住宅は「省エネ性能の高い住宅※2」のみ住宅ローン減税の対象 |
| 【立地に関する条件】 令和10年以降に入居する場合、災害レッドゾーンに建つ住宅が住宅ローン減税の対象となるのは建替え・中古住宅購入・リフォームのみ | 新築災害レッドゾーンとは土砂災害特別警戒区域などのことで、新築住宅でも令和8年・令和9年に入居する場合は住宅ローン減税の対象 |
※1 子育て世帯・若年夫婦世帯とは以下の世帯のことで、住宅ローン減税額がより優遇される(減税額が高額になる)可能性があります。
優遇を選ぶ場合には床面積50㎡以上、優遇を選ばない場合には床面積40㎡以上が適用条件となります。
- 子育て世帯:19歳未満のお子さまがいらっしゃるご家庭
- 若年夫婦世帯:ご夫婦のどちらかが40歳未満のご家庭
※2 「省エネ性能の高い住宅」とは、以下の住宅のことです。
住宅ローン減税の適用を受けるためには、省エネ性能を証明する書類を取得・提出する必要があります。
| 省エネ性能 | 概要 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 長期にわたって優良な状態で使用できる住宅で、耐久性が高い点が特徴 |
| 認定低炭素住宅 | CO2排出量を抑制できる住宅で、高性能の省エネ設備を導入する点が特徴 |
| ZEH水準省エネ住宅 | エネルギーの使用量・創出量のバランスをおおむねゼロにできる住宅で、高い断熱性能・省エネ性能が特徴 |
〈参考〉国土交通省ウェブサイト『住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~』
住宅ローンを利用せずに住宅購入などをする場合にも減税制度がある
住宅ローンを利用せずにマイホームを購入する場合の減税制度「認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)」もあり、令和8年度以降も実施されます。(令和8年度から3年間)
「認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)」の適用条件は詳しく公表されていないため、現時点で想定えきる条件を紹介します。
| 対象となる住宅 | 適用条件 |
| 認定住宅等※の新築or購入 | ・新築後、使用されたことのない認定住宅※の購入 ・新築から6ヶ月以内に入居 ・住宅の床面積が40㎡以上 ・所得2,000万円以下 ・(2つ以上の住宅所有者)主に居住する住宅 ・過去3年間・以後3年間に譲渡所得の課税の特例を受けていない ・災害レッドゾーン以外の立地に建つ住宅 |
〈参考〉
・国税庁ホームページ『No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)』
・国土交通省ウェブサイト『令和8年度税制改正』令和8年度国土交通省税制改正概要3ページ
※認定住宅等の種類は、以下のとおりです。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- 特定エネルギー消費性能向上住宅(断熱等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上の住宅)
〈参考〉国税庁ホームページ『No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)』
新築住宅のみに適用される減税制度ですが、以下の額の10%が減税となるため、現金一括でマイホームを購入する場合も忘れずに手続きをしてください。
【以下の額の10%が減税となる】
床面積(㎡)×45,300円(上限650万円)
住宅ローン減税の減税額シミュレーション

住宅ローン減税の延長を見込める理由、住宅ローン減税の概要などを確認してきたので、次に具体的な減税額もシミュレーションして紹介します。
住宅ローン減税の計算方法|所得税・住民税が減税となる
住宅ローン減税の計算方法は以下のとおりで、10年間or13年間にわたって所得税が減税されます。
【住宅ローン減税の計算方法:年末の住宅ローン残高×0.7%】
年末の住宅ローン残高は、金融機関が毎年10月頃に発行する「年末残高証明書」で確認します。
住宅ローン減税のシミュレーションする際には、返済予定表で各年の年末残高を確認してください。
また、住宅ローン減税の減税額には上限があるため、一覧表で紹介します。
【新築住宅の住宅ローン減税額】
| 省エネ性能 | 減税額の上限 (子育て世帯・若年夫婦世帯) |
|---|---|
| ・認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 | 【13年間】 4,500万円×0.7%=31.5万円 (5,000万円×0.7%=35 万円) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 【13年間】 3,500万円×0.7%=24.5万円 (4,500万円×0.7%=31.5万円) |
| 省エネ基準適合住宅 (令和8年・9年末までに建築確認を受けて令和9年末までに居住) | 【13年間】 2,000万円×0.7%=14万円 (3,000万円×0.7%=21万円) |
| 省エネ基準適合住宅 (9年末までに建築確認を受けて令和10年以降に居住) | 【10年間】 2,000万円×0.7%=14万円 |
【中古住宅購入・リフォームの住宅ローン減税額】
| 省エネ性能 | 減税額の上限 (子育て世帯・若年夫婦世帯) |
|---|---|
| ・認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 ・ZEH水準省エネ住宅 | 【13年間】 3,500万円×0.7%=24.5万円 (4,500万円×0.7%=31.5 万円) |
| 省エネ基準適合住宅 | 【13年間】 2,000万円×0.7%=14万円 (3,000万円×0.7%=21万円) |
| 上記以外の住宅 | 【10年間】 2,000万円×0.7%=14万円 |
〈参考〉国土交通省ウェブサイト『令和8年度税制改正』令和8年度国土交通省税制改正概要3ページ
ご自身の所得税額(年間)が上限額を上回っている場合は、住民税も減税されます。
【住民税の減税額】
所得税額−所得税減税額=住民税の減税額(上限97,500円)
〈参考〉総務省ホームページ『新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。』
住宅ローン減税の減税額シミュレーション

子育て世帯・若年夫婦世帯以外の世帯が認定長期優良住宅を新築すると仮定し、住宅ローンの年末残高・所得税額の例を設定して、シミュレーションを紹介します。
【住宅ローンの年末残高:3,000万円、所得税額20万円】
「所得税の減税額>1年間に支払った所得税額」となる場合、1年間に支払った所得税額が減税額の上限となります。
- 所得税の減税額:3,000万円×0.7%=21万円≠20万円
- 住民税の減税額:なし
【住宅ローンの年末残高:3,500万円、所得税額30万円】
「所得税の減税額が上限以内」「減税額<1年間に支払った所得税額」となる場合、住民税も減税されます。
- 所得税の減税額:3,500万円×0.7%=24.5万円
- 住民税の減税額:30万円−24.5万円=5.5万円
【住宅ローンの年末残高:4,800万円、所得税額45万円】
この例は、住宅ローンの年末残高が4,500万円超のため、所得税の減税額は上限額の31.5万円となります。
また「減税額<1年間に支払った所得税額」となるため住民税も減税されますが、住民税の減税額上限も超過しているため、住民税の減税額は97,500円となります。
- 所得税の減税額:4,500万円×0.7%=31.5万円
- 住民税の減税額:45万円-31.5万円=13.5万円≠97,500円
住宅ローン減税で所得税が還付されるまでの流れ|1年目・2年目以降

ここで、「住宅ローン減税が延長される見込みがあることはわかったけど、手続方法がよくわからない。どのような準備が必要?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
住宅ローン減税は、適用条件に該当する方全員が活用できる制度ですが、期限までに手続きをする必要があります。
「1年目・2年目以降の手続きが違う」など複雑な制度なので、手続きの流れも一緒に確認しましょう。
【1年目】住宅ローン減税の適用を受けるためにご自身で確定申告が必要
住宅ローン減税の適用条件に該当する場合、1年目は以下の流れで手続きをします。
【所得税還付までの流れ】
マイホーム購入の手続き中:工事請負契約書などの書類をすべて保管しておく
↓
マイホームを購入した年の10月ころ:金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等
証明書」が届くので、保管しておく
↓
マイホームを購入した年の年末or翌年の年始:勤務先から源泉徴収票を受け取り、保管しておく
↓
マイホームを購入した年の翌年:3月15日までに保管しておいた書類を使用してご自身で確定申告をする
↓
確定申告書を提出後、1ヶ月前後で所得税の減税額が指定口座(ご自身が指定した口座)に還付
住民税の減税額は、マイホームを購入した年の翌年の住民税額から減税(手続き不要)
【2年目以降】年末調整時に勤務先へ書類提出が必要

マイホーム購入の翌年からは、勤務先が住宅ローン減税の計算を含めて年末調整を行い、所得税が還付されます。
【所得税還付までの流れ】
マイホーム購入の翌年10月頃:以下の書類が郵送される
・国税庁:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・金融機関:住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
↓
勤務先に上記の書類を提出
↓
勤務先が住宅ローン減税の計算を含めて年末調整を行う
↓
以下どちらかの方法で所得税が還付される
・所得税の減税額を含めて12月or1月の給与が計算される
・所得税の減税額が現金で還付される
↓
住民税は、翌年の住民税額から減税(手続き不要)
住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類
住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類は、以下のとおりです。
| 年 | 必要書類 |
|---|---|
| 1年目 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・源泉徴収票 ・工事請負契約書or売買契約書 ・(土地を購入する場合)土地の登記事項証明書と売買契約書 ・補助金を活用した場合は補助金の額がわかる書類 ・マイホーム購入資金の贈与を受けた場合には贈与額がわかる書類 ・マイナンバーカードの番号を照合するための書類 ・住宅の省エネ性能などを証明する書類 |
| 2年目 | ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 |
〈参考〉国税庁ホームページ『確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)』>住宅控除関係「特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】
ちなみに、住宅ローン減税の手続きを忘れてしまった場合でも、5年以内であれば手続きが可能です。
- 1年目の確定申告を忘れた場合:過去5年以内の確定申告を提出可能
- 2年目の年末調整に住宅ローン減税を含めるのを忘れた場合:5年以内にご自身で確定申告をする
住宅ローン減税に関する不明点やお困りごとがある場合は、お住いの地域を管轄する税務署に問い合わせをしてください。
令和8年度の住宅ローン減税延長Q&A

最後に、マイホームの購入・住み替えなどにあたって住宅ローン減税の活用をご希望の方から、イエステーションがよくいただく質問・回答を紹介します。
Q.今後、住宅ローン減税はいつまで続く?なくなることはある?
A.今後の「住宅ローン減税が延長される期間」「住宅ローン減税終了の可能性」については、予測をしづらい状況です。
ただし、近年の地価上昇・住宅価格上昇・金利上昇などの傾向から、政府が住宅の購入などに対するサポートを何らかのかたちで継続していくことは想定できます。
Q.令和8年度以降の住宅ローン減税の内容は、令和7年度以前にも適用される?
A.令和8年度以降の住宅ローン減税の内容が、令和7年度以前の過去にさかのぼって適用されることはないのが通例です。
住宅ローン減税は、居住年に応じた制度内容の適用を受けていくことになります。
Q.住宅ローン減税の適用期間が終わるとどうなる?
A.住宅ローン減税の適用期間が終わると、所得税・住民税の減税がなくなります。
住宅ローン減税は、「住宅に対する投資の負担感が最も重い初期投資期間の負担軽減」を目的に実施されているため、10〜13年間限定の制度です。
住宅ローン減税終了をきっかけにして住み替えなどをする場合には「譲渡所得税の負担を軽減する特例」などがあるため、活用を検討しましょう。
譲渡所得税の負担を軽減する特例について、こちらの記事で詳しい内容を確認できます。
〈関連ページ〉自宅売却の税金がかからない場合は主に2パターン|3000万円控除の特例、申告方法など簡単解説
宮城県・福島県・茨城県でマイホームの住み替えなどを検討中の方は、イエステーションへお問い合わせください。
地域最大級の不動産売買実績を活かし、売却・購入の同時進行などをサポートいたします。
Q.住宅ローン減税の期間中に繰上返済をする場合、減税額はどうなる?
A.住宅ローン減税は住宅ローンの年末残高に応じて減税額を計算するため、住宅ローン減税の期間中に繰り上げ返済をすると、減税額が減少します。
住宅ローン減税の減税率は0.7%のため、住宅ローン金利が0.7%を下回るほど恩恵が大きくなります。
繰上返済の時期は、ご自身の住宅ローン金利に応じて、「住宅ローン減税の恩恵を受ける」「住宅ローンの金利総額を減らす」どちらを優先するべきかをシミュレーションして判断することをおすすめします。
Q.住宅ローン減税の期間中に借り換えをする場合、どのような手続きが必要?
A.住宅ローン減税の期間中に借り換えをする場合、最新の年末残高証明書などを使用して減税額の計算をします。
ただし、以下のように通常とは違う手続きが必要な場合もあります。
- 勤務先が年末調整をするまでに金融機関発行の年末残高証明書が送付されない場合、ご自身で確定申告をする
- 借り換え後の住宅ローンが借入期間10年以下の場合は、住宅ローン減税が適用されないため勤務先への書類提出は不要 など
Q.ふるさと納税をすると住宅ローン減税で損をするって本当?
A.ふるさと納税も所得税を減税できる制度です。
また、ふるさと納税の返礼品に対する寄付額は、通常の購入額の3倍ほどが一般的です。
「返礼品を通常よりも高額で受け取り、住宅ローン減税で減税できる額が減る」という考え方をすると、損をするイメージとなります。
「所得税・住民税の支払額>所得税・住民税の減税額」となる場合以外は、ふるさと納税による所得税の減税効果はないと考えておきましょう。
まとめ
住宅ローン減税は、令和8年度から5年間の延長が決定しました。
令和8年1月〜3月の期間に住宅ローン減税に関する法律が改正されるため、詳細の公表・令和8年度以降の住宅ローン減税施工は3〜4月頃となります。
そのため、当記事は政府が最新情報を公表する度に内容を更新してお伝えしていきます。
住宅購入などに関する書類は保管しておき、住宅ローン減税を活用できるように準備していきましょう。







