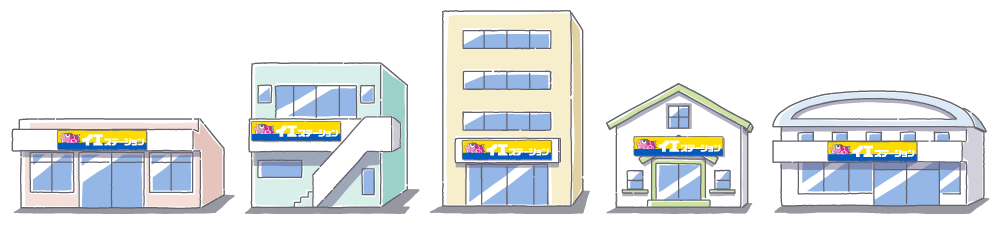毎年、夏から秋にかけて日本列島を襲う台風。その強力な風雨は、私たちの生活に甚大な影響を及ぼします。しかし、台風の被害は「運」だけで決まるものではありません。事前の備えと、いざというときの適切な行動が、あなたの命と財産を守る鍵となります。
「まだ先のこと」と思っていると、あっという間に台風はやってきます。いざ接近してからでは、慌てて準備をしても手遅れになることも少なくありません。今こそ、落ち着いてできることから対策を始めましょう。
なぜ今から対策が必要なのか
台風対策と聞くと、「大げさな」「台風が来てからでも間に合うだろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、被害を最小限に抑えるためには、早めの準備が不可欠です。
台風が近づいてくると、スーパーやホームセンターは食料や防災グッズを買い求める人々でごった返します。品切れになる商品も続出し、必要なものが手に入らない事態に陥ることも珍しくありません。また、強風が吹き始める中での家の外での作業は非常に危険です。ベランダの片付けや窓の補強など、屋外での作業は風が強まる前に終えておく必要があります。
さらに、台風の進路や規模は常に変動します。急な進路変更や勢力の拡大によって、当初の予想よりも大きな被害が出る可能性も否定できません。このような不測の事態にも対応できるよう、余裕をもって準備を進めることが賢明な判断と言えるでしょう。
台風に備える3つのステップ
台風対策は、大きく分けて「事前準備」「台風接近時の行動」「台風通過後の対応」の3つの段階に分けられます。それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
ステップ1:事前の準備(今すぐできること)
この段階が最も重要です。台風がまだ遠くにあるうちに、できる限りの準備を整えておきましょう。
1. 自宅の安全対策
・窓ガラスの補強と飛散防止:
▸飛来物による窓ガラスの破損を防ぐため、雨戸やシャッターがある場合は必ず閉めましょう。
▸雨戸がない場合は、ガラス飛散防止フィルムを貼るのが効果的です。ガムテープを窓に「米」の字型に貼る方法は、ガラスが割れるのを防ぐ効果は薄いとされていますが、破片の飛散を抑える効果は期待できます。
・ベランダ・庭の片付け:
▸植木鉢、物干し竿、サンダル、空のゴミ箱、レジャー用品など、風で飛ばされやすいものはすべて室内にしまいましょう。これらが飛来物となり、窓ガラスを割ったり、近隣に被害を与えたりする可能性があります。
・排水溝・雨どいの清掃:
▸葉や泥で排水溝や雨どいが詰まっていると、雨水が逆流し、浸水被害につながることがあります。台風が来る前に、ゴミを取り除き、スムーズに水が流れるようにしておきましょう。
・カーポート・自転車の固定:
▸カーポートは風の影響を受けやすく、破損する危険があります。可能であれば、あらかじめ支柱を補強しておきましょう。自転車は倒れないようにロープで固定するか、屋内に避難させましょう。

2. 非常持ち出し袋の準備と食料の確保
・非常持ち出し袋:
▸災害発生時にすぐに持ち出せるよう、最低限必要なものをリュックサックなどにまとめておきましょう。
▸必需品: 飲料水(1人1日3リットル、3日分を目安)、非常食(調理不要なもの)、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、常備薬、着替え、タオル、ウェットティッシュ、軍手、貴重品(現金、健康保険証のコピーなど)。
▸家族構成に合わせて追加: 赤ちゃんのいる家庭なら粉ミルクやおむつ、高齢者がいる家庭ならお薬手帳や持病の薬、ペットがいる家庭ならペットフードやケージなど。
・備蓄食料:
▸停電に備え、調理しなくても食べられるものを数日分備蓄しておきましょう。缶詰、レトルト食品、カップ麺、栄養補助食品などが適しています。
▸水道が使えなくなることも想定し、飲み水だけでなく、生活用水も確保しておくと安心です(お風呂に水を張っておくなど)。
3. 情報収集と避難場所の確認
・ハザードマップの確認:
▸自治体が作成しているハザードマップ(災害の危険性を示した地図)を必ず確認しましょう。洪水、土砂災害、高潮など、自宅周辺にどのようなリスクがあるのかを事前に把握しておくことが、命を守る第一歩です。
・避難場所・避難経路の確認:
▸災害が発生した際に、どの避難所へ行くのか、どのような経路で向かうのかを家族で共有しておきましょう。特に、夜間の避難に備え、昼間のうちに実際に歩いてみることも有効です。
▸避難場所は、自宅の立地や災害の種類によって変わります。複数の避難場所を想定しておくと安心です。
ステップ2:台風接近時の行動
気象情報に注意を払い、冷静に行動することが大切です。
・最新情報の確認:
▸テレビ、ラジオ、インターネット、スマートフォンの防災アプリなどを活用し、気象庁や自治体が発表する最新の情報をこまめにチェックしましょう。
▸特に、暴風警報、大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報などの「警報・注意報」や、避難指示には注意が必要です。
・屋外での作業はしない:
▸風が強まってきたら、絶対に屋外での作業はしないでください。看板などが飛んでくるなど、二次災害の危険が高まります。
・無理な外出は避ける:
▸不要不急の外出は控えましょう。特に、車での移動は冠水した道路に閉じ込められたり、強風にあおられたりする危険があります。
ステップ3:台風通過後の対応
台風が去った後も油断は禁物です。
・安全確認:
▸自宅の周りを点検する際は、切れた電線や倒木などに注意し、安全を十分に確認してから行いましょう。
▸建物に大きな損傷がある場合は、安易に立ち入らないでください。
・片付け・復旧作業:
▸片付けをする際は、感電や怪我に注意して慎重に行いましょう。
▸災害ゴミの出し方など、自治体の指示に従って適切に処理しましょう。
台風対策の盲点:見落としがちなポイント
ここからは、多くの人が見落としがちな、より実践的な対策について掘り下げていきます。
1. 家電・インフラの保護
・電源プラグを抜く: 落雷による過電流から家電を守るため、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。特にパソコンやテレビ、冷蔵庫などは重要な家電なので、忘れずに対策してください。・ガス・水道の元栓を締める: 大規模な被害が予想される場合は、ガスや水道の元栓を締めておくことも検討しましょう。ガスの元栓を締めることで、地震などによる二次災害でガス漏れが発生するリスクを減らすことができます。
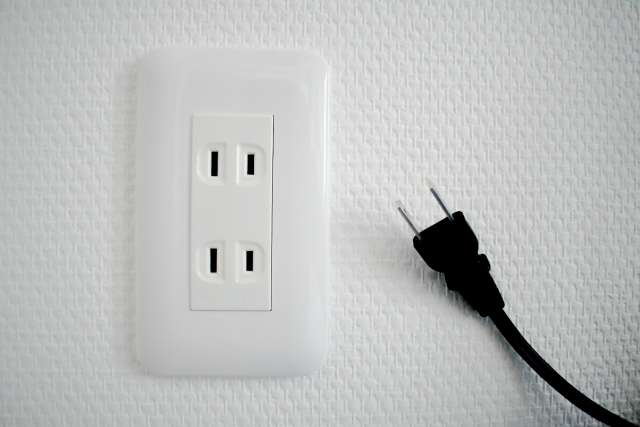
2. 車の対策
・安全な場所への移動: 地下駐車場や低地に駐車している場合は、高台や立体駐車場など、浸水の心配がない場所に移動させましょう。
・車載品の見直し: 万が一車内で過ごすことになった場合に備え、車載品(懐中電灯、モバイルバッテリー、非常食など)を見直しておきましょう。
3. 災害情報の多角的な入手
・携帯ラジオの準備: 停電時には、スマートフォンやテレビが使えなくなる可能性があります。電池式の携帯ラジオは、災害時の貴重な情報源となります。
・家族との連絡手段: 離れて暮らす家族と、災害時の安否確認の方法や集合場所を事前に決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル(171)や、SNSの安否確認機能などを活用する方法も検討してください。
4. 高齢者や要配慮者への配慮
・避難のサポート: 高齢者や障がいのある家族がいる場合、避難場所への移動に時間がかかる可能性があります。早めの避難を心がけ、必要であれば、自治体や地域の支援を事前に確認しておきましょう。・持ち出し袋のカスタマイズ: 持病の薬や医療器具など、個別のニーズに応じたものを追加で持ち出し袋に加えておくことが不可欠です。

まとめ:備えあれば憂いなし
台風は、私たちの暮らしに大きな影響をもたらしますが、適切な対策を講じることで、その被害を大きく減らすことができます。
「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、事前の準備が何よりも重要です。
今日からでもできることはたくさんあります。この記事を参考に、まずは「ベランダの片付け」や「非常食のチェック」など、できることから少しずつ始めてみてください。それが、あなた自身と大切な家族、そして地域全体の安全につながります。
もし、「もっと詳しく知りたい」「うちの地域はどんな災害に弱いんだろう?」といった疑問があれば、お気軽に教えてください。一緒に確認していきましょう。
ぜひ最寄りのイエステーションへご相談ください